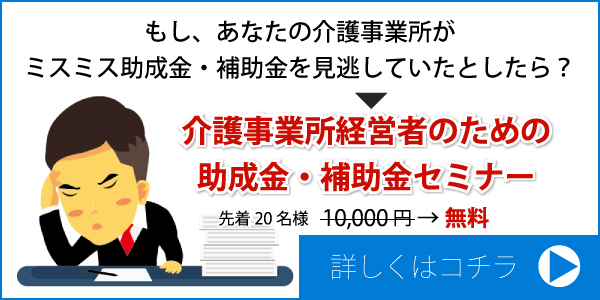あけましておめでとうございます。
今年はまた本を出す準備をしていこうと思います。次回の私の書こうと思っている本は私の顧問先で実際に起こった話を中心に、読みやすい読みもの風のものにしていこうと思っています。ブログもその本のためにも大変重要なツールだと思っています。昨年以上にこのブログから情報発信していこうと思います。
さて、今日は、「障害者雇用促進法」という法律についての話です。
法律の名称を言ってもピンと来ないでしょうか?最近、公務員が障がい者の雇用を水増ししていて問題になったという事件がありました。民間企業は障がい者を一定数以上雇っていないと罰金を支払わないといけないのに、公務員は罰則の適用がないという、民間企業からしたら憤慨するのがもっともな話です。そのことが規定されている法律が「障害者雇用促進法」です。
さて、このブログではその国や地方自治体で起こっているそうした問題にコミットするのではなく、あくまでも中小企業目線で書いているブログです。今回もその視点で見ていこうと思います。

まず、障害者を雇わないといけない「障害者雇用率」についてみていきましょう。
障害者雇用率は昨年、平成30年4月から、民間企業は2.0%から2.2%に引き上げられました。この引き上げによって、民間企業では、平成30年3月までは従業員数50名以上で1名の障害者雇用が必要だったのが、45.5人以上で障害者1名となりました。障害者雇用のハードルが下がったということです。
ちなみに、国や地方公共団体では、平成30年4月以降は2.5%に引き上げられました。つまり、40名につき1名は障害者を雇わないといけないということです。
ここで言っている「従業者数」というのはどういう意味でしょうか。労働局のHPから抜粋してみましょう。
常用労働者・・・1年以上継続して雇用される者(見込みを含みます。)をいいます。そのうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者については、1人をもって0.5人の労働者とみなされます。なお、1週間の所定労働時間が20時間未満の方については、障害者雇用率制度上の常用労働者の範囲には含まれません。
おおむね雇用保険の一般被保険者が「常用労働者」で、週の労働時間が20時間以上30時間未満の「短時間労働者」は0.5人でカウントするということのようです。
雇用保険に加入している人の数でカウントしていって、45.5人以上の場合、障害者を一人雇わないといけないということになります。
また、一般的に精神障害者は週の労働時間が週20時間以上30時間未満になるケースが多いとされていて、精神障害者に限っては、週の労働時間が20時間以上30時間未満であっても0.5人ではなく1人でカウントするとなっています。
では、この障害者雇用率を満たさなかった場合、どうなるのでしょうか?この場合、「障害者雇用納付金」と呼ばれる罰金を支払うことになります。では、いくら支払うのでしょうか?
不足する障害者1人につき、1か月あたり5万円を支払うことになります。
逆に、一定数以上の障害者を雇っている場合、報奨金をもらえることもあります。
高齢・障害・求職者雇用支援機構のHPによると、以下のように書かれています。
「常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に21,000円を乗じて得た額の報奨金が支給されます。」
対象はあくまでも、従業員数(ほぼ雇用保険被保険者数)が100人以下の事業所に限られますが、4%以上の障がい者を雇っていると、超過した人数に応じて21,000円が支給されます。
また、障害者の雇用をめぐっては助成金もあります。特定求職者雇用開発助成金です。その他にも、障害者を雇用すると受給できる助成金が多く存在します。その辺については、私の以前のブログをご参照ください。↴
また、東京都に関しては国の特定求職者雇用開発助成金を受給すると東京都独自の助成金として「東京都障害者安定雇用奨励金」というのが受給できます。受給額はなんと150万円(精神障害者の場合には180万円)です。
特定求職者雇用開発助成金は短時間労働者(つまり、週の労働時間が20時間以上30時間未満)でもでる助成金です。仮に、短時間労働者を雇い入れた場合、国から(特定求職者雇用開発助成金として)80万円、東京都から150万円であわせて230万円でます。
国の助成金は2年間雇って受給できるものなので、たとえば、週の労働時間を20時間として2年間雇ったとします。時給1000円で計算すると、以下のようになります。
1,000円×20時間×4.5週=90,000円
90,000円×24ヶ月=2,160,000円
つまり、助成金受給額とほぼ同じか、むしろ助成金の金額の方が多いことになります。
障害者雇用に当たっては、こんなことも知っておくだけで違うかもしれません。
今日は「障害者雇用」について、中小企業の視点から考えてみました。